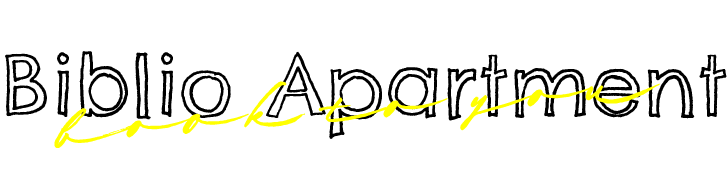『庭とエスキース』
-
2019-11
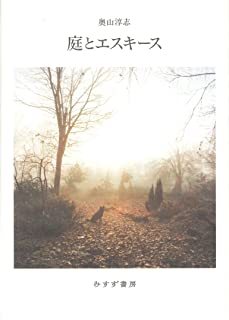
内容はよくわからないのに、これはいつか読まないといけない本だという予感のする本ってある。『庭とエスキース』がそうだった。この美しいタイトルと表紙の写真から、フェルメールのような絵を静かに密かにアトリエで描く女性の話なのかなと勝手な想像をしていたが、ページを開いてみると全く違う世界が広がっていた。著者は、写真家の奥山淳志さん。その文章は一番身体に染み入る温度の水のようで、まだ少し暑かった今年の秋の初め頃に、ごくごくと飲むように毎日読んだ。そして、毎日ぼろぼろ泣いていた。
本の内容に少しだけ触れると、画家を目指しながら、自給自足の庭を作り、北海道の丸太小屋で一人生活をしている弁造さんのことを、写真を撮りに通う奥山さんが綴った本だ。奥山さんは最初からこのような本を書こうと思っていたわけではなく、あくまで写真を撮るのが目的だった。そうして写真集が完成し、そのあとで、みすず書房の方からお声がかかったそうだ。「弁造さんのことを書いてみませんか?」と。
思い出した順番に書かれているので、きれいに時系列に並んでいるわけではない。しかし、読み進むにつれて奥山さんが弁造さんに会い続けることで「わかりたい」と思ったことが確実に深まっていくのがわかる。奥山さんの迷いに迷った末に「これしかない」と選んだであろうひとつひとつの言葉は、とてもリアルで自分もいろんな季節に弁造さんに会いに行っているようなそんな気持ちにさせてくれた。そして弁造さんが大好きになっていった。カバーを外すと表れるのは黄色の表紙。少し頼りない薄さだけれど、少々乱暴に扱っても味になりそうな画用紙みたいな紙は、弁造さんそのものだと思った。
失礼かもしれないが、この本自体が奥山さんのエスキースのようにも感じた。一般的には下絵と訳される言葉だが、弁造さんのエスキースはとても完成度が高い。いつか完成することを疑わず、でも迷い、悩みながら一歩一歩筆を進めていく。こんな美しい物語を読んでいると、完成することなんて別にどうでもいいのではないかとさえ思ってしまうし、実際そうなんだとも思う。しかしそれは、エスキース「で」いい、そう思っている人間には決して描けないものなのだということも、同時に教えてくれる。私たちは、生きて老いていつか死ぬ。病気にもなるだろう。そんな道を照らしてくれるであろう、弁造さんというこの強烈な人の「生きること」を見つけてくれた奥山さん、控えめに言ってもブラボーだ
『庭とエスキース』奥山 淳志