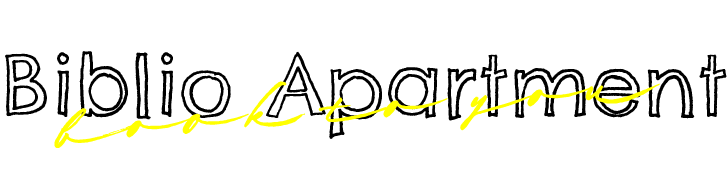『キッチン』
-
2019-06
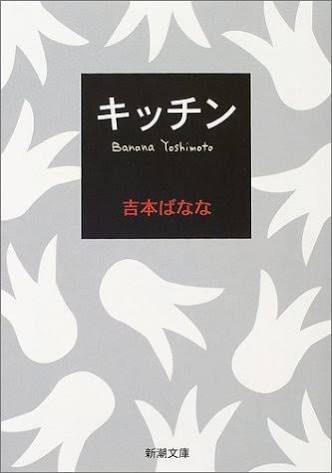
札幌に引越した日、彼が私にこの本を勧めてきた。吉本ばななは読んだことがなく、「キッチン」「ばなな」という言葉から、「キャベツ」やあるいは「それからはスープのことばかり考えて暮らした」みたいな空気感の物語を想像した。これからふたりで新しい暮らしを作っていくために、私に共有したいイメージがあるのだな、と。
そんな予想というか期待ははずれ。読んでも読んでも大切な人が死んでばっかりだった。ふたりの念願の新しい生活が始まるというときに、私に選んだ本がこれか。
勝手に期待していた私は単純で、一方彼は特に意味なくこの本がたまたまあって彼なりに気に入っていたから渡しただけなのだろう。故郷や家族、仕事を捨てなければならなかった私と違って、彼はそれまでの延長で私達の新生活を当たり前で自然なこととして認めているから、この本が私への1冊目であることは特段意識することではなかった。だからホッとしたとかガッカリしたとかではなくて、この本を読み終える頃には私にとっても、新しい生活がとびきり普通のことになっていた。
「キッチン」は暗い話だけれど、ただひたすらに暗いわけではない。でもその暗さもそのあとのことも、私にはまだわからないから、いやだ、こわいという感情を引きずって、読みきった時は隣で寝る夫の寝息をかぶって気を紛らわせながら眠った。
・
キッチン (吉本ばなな)