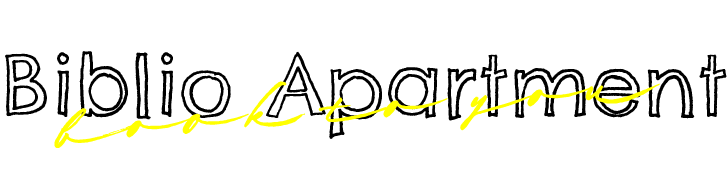『死にカタログ』
-
2020-01

「過程を示すこと」の面白さに改めて気づいたのはこの本だった。
死ぬって、「今日のテスト死んだ…」とか「このケーキ死ぬほど美味い」とか
良くも悪くも極限状態をあらわす言葉としてよく使われる。
それって「死」を軽んじているわけではなくて、
なんかこう、大げさに言いたいときにちょうどいい言葉だから
使っちゃうんだよねー、くらいの軽めの気持ちなんじゃないかと思う。辞書とか何も見ずに勝手にしゃべってるけど、
息が止まって、肺に酸素がいかなくなって、血の流れが止まって、心臓の動きが止まって、
生命活動が停止したその瞬間を「死」と呼ぶならば
死ぬってなんてあっけないんだろう、と感じてしまう。
だから、「死」を重いものにしているのは
その瞬間より前に起こったすべての出来事の積み重ね、人生の蓄積物。
「過程」。今際の際に本当に走馬灯は流れるのか。
まだ死にそうになったことがないのでそんなこと確かめようがないけど、
いまから死を迎えようとしている人がその重みを感じる瞬間があるとするなら
たぶんその走馬灯がそうなんじゃなかろうか。王道の少年マンガとかを読んでいると、だいたい1回は
「お前に何がわかる!!」
みたいな台詞を叫んでいる悪役もしくはライバル的位置付けのキャラクターが出てくるが、
これも人生のことを言っている場合が多い。
そりゃそう言いたくもなるよな。あんたの人生全部知ってるわけじゃないんだもの。
※決してディスっているわけではありません。そういう熱い展開は大好きです。死んだ後の世界は言ってしまえばファンタジーなのでいくらでも想像できる。
でも、死ぬ前の世界は間違いなくリアルに起こったことで、もしかしたら想像できるファンタジーの
何倍ものパターンが存在する、ある意味すごい世界なのでは?「死」という結果に行きつくまでの「過程」、それが人生。うん、なんかしっくりきた。
…おかしい。
死ぬまでの道のりを至極真面目に、そしてこんなにお茶目に
描いている文平さんの本はやっぱり面白いやって言おうとしていたのに。「死」って言葉は、見ただけで質量を感じる、特殊なニホンゴだな。
『死にカタログ』寄藤文平・著